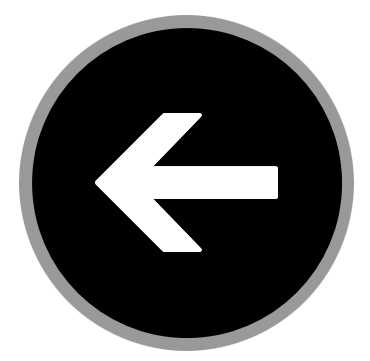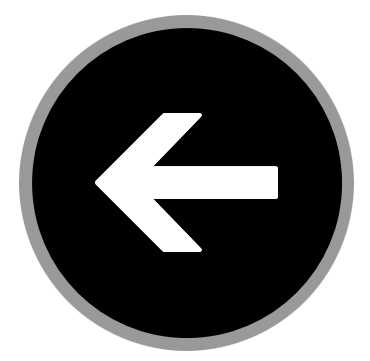「てめぇのために痩せてんじゃねぇよ」
四王天廿(シオウテン・ニジュウイチノマエ)先輩は変わってしまった。これが本当にあの廿先輩の口から出た言葉だろうか。私は廿先輩を愛している。女性同士の憧れのナントカとか女子校的なエレガンスなアレとかではないし、完全に性的に愛していると言える上に廿先輩さえ良ければ二人で結構ダイナミックなことまで出来る自信がある。普通の奴らから見たらこういうのはケッコウ気持ち悪いことなのかもしれないけれど人を好きになるっていうのはこういうことだと思うし私は全く恥じてないし恥じる意味もわからない、ただ問題なのが私が愛しているのが今の廿先輩なのか4年前の廿先輩なのか自分でもよくわからないことだ。
廿先輩がアメリカに発ってから4年、廿先輩は高2で、私は高1になっていた。正直なところ久しぶりに見た廿先輩の190センチの身長にはかなり驚いたけれど、それ以上に驚いたのはあの天真爛漫な廿先輩がテレビの影響で飼ってみたはいいものの大人になるまで育ててみたら凶暴過ぎてとても一緒に寝られないというよりは同じ部屋で飼うこともままならなくなったリアル・アライグマみたいな鋭い目付きになっていてそれはどうしようもなく私の心臓を貫いた。
「そうだね、僕のためじゃないね、ごめんね」
こいつだ。最上一(サイジョウ・ハジメ)だ。廿先輩が帰国して1年。私がやっとの思いで同じ高校に入学するまでのたったの1年でここまで廿先輩を変えてしまったのだ(と思う)。
廿先輩と同じ学校に入って数ヶ月、学年が違う廿先輩とやっとの思いで(後ろに立っていてもなんでこいつここにいるんだろうとは思われない程度に)親しくなれたのはここ数ヶ月。廿先輩は学校帰りには常に最上一が住み込むゲームセンターにいる。彼女達はいつも通り音ゲーをやっていた。私もいる。私は常に二人が音ゲーをやっているのをロシア人しかいない個室に放り込まれた唯一人の日本人みたいにただただ笑顔かつ無言かつ脂汗一杯で立ち尽くしていた。
廿先輩と再び親しくなるのは簡単だと思っていた。私の中の廿先輩は4年前の廿先輩で止まっている。エサをあげなくても目に止まるだけで誰にでもシッポを振って近づいてくる警戒心が無さ過ぎるパグみたいな廿先輩(過去形)は私が必死こいて捻出したTwitterの面白ツイートの話題にただ一言「そう」と2文字を返してくれる類のアレになっていた。
心が折れそうだ。心も折れそうだ。必死こいて先輩と同じ高校に入学した私と、同じく必死こいて先輩にお近づきになろうと頑張ってきたここ数ヶ月の私はなんなんだろう。
「あ、廿先輩、フルコン、です、ね。」
思い切ってもう1行送ってみた、同じく「そう」と2文字が返って来た。廿先輩は私がこの1行を発するまでにすり減らした魂と垂らした脂汗の量がわかっているのだろうか。辛い。辛い。大丈夫、私は生きている。
「あの…私、天下迎えに行くんで、そろそろ行きますね。」
「そう」
「いつも大変だね、また明日ね、天上ちゃん」
クソ、クソ、なんで廿先輩は二文字しか返してくれないんだ。最上一、おまえは私をちゃん付けで呼ぶな!なんでおまえの方が廿先輩より沢山話してくれるんだ。クソ、クソ、大丈夫、私は生きている。
「出たよ…」
自分のロッカーにスマホを取りに行った私に名前を覚えていないクラスメイト3名が3文字を投げかけた。私はロッカーに鍵をかけないタチ(鍵は失くした、再発行の手続きをしに大人と喋るのは怖い)なのでスマホ忘れはけっこう危険だったかもしれない、往復の電車賃だって馬鹿にならない。何よりも授業が終わった後にクラスメイトに会うのも嫌だった。案の定ありがたい言葉を三文字も貰ってしまった。大丈夫、私は生きている。でもここからは早く抜け出したい。
「釵売天上(チタニウム・テンジョウ)です、うさぎ組の釵売天下(チタニウム・テンゲ)を迎えに来ました」
「はい、天上ちゃん、いつもありがとう、ちょっと待っててね」
私の学校から天下の学校までの距離の短さは唯一の救いだ。それに、この学校の教員達の笑顔は、なんだか道端のお地蔵様みたいで癒される。私も常にあんな笑顔で過ごせたらいいのに。
「おねえちゃん!どこ!?」
「いるよ、いるよ、目の前にいるよ」
天下は山積みの直方体に包まれてた。いつも手ぶらなのに何やってるんだろう。
「それ、何?」
「みんながたんじょうびプレゼントくれたの!」
「あ、そう」
「プレゼントだよ!」
「わかったから」
質問した直後には私も気が付いていた。9月17日、今日は私達の誕生日。私達は数時間違いで産まれた姉妹。数時間の差で私はめでたくお姉ちゃんに、天下はめでたく妹になった。私は今日誰からも祝われていない、天下の荷物を見ても口にするまでピンと来なかった。天下は祝われている、ただそれだけの違いだ。大丈夫、私は生きている。
「それ、貸して、半分持つから」
「うんー、じゃあはんぶんあげるね!」
「いらないから、それ意味ないから」
私達二人は直方体を掲げながら商店街を歩く、近所の人達は昔私達のことを釵売天上天下(チタニウム・テンジョウテンゲ)姉妹と呼んでいたと言うが、私達が物心つく頃には皆姉と妹の違いに気付いたのか、誰も面と向かって私達のことをそうは呼ばなくなっていた。
「おねーちゃーん!」
ガラスの向こうからくぐもった声で天下が鳴いていた。私がショートカットで入ったスーパーのガラス扉に8ビットゲームのキャラみたいに天下が詰まっている。
「両手が塞がっている時はおしりで押せばいいんだよ」
「こう?」
ガラス扉に股間を押し付けたまま天下が聞き返す。
「…もういいよ、私開けるからちょっと待って」
そういえば天下に荷物を持たせて歩いたのは初めてかもしれない。私は直方体を下ろしてガラス扉を引いた。
「ありがとーん!」
考えてみればこうして私が二人で並んで歩くようになったのもつい最近のことだ。かなり長い期間母に任せきりだった私も、さすがに罪悪感を覚えてきたのだ。名前のことも相まって、私達は幼いころ二人でワンセットみたいな扱いを受けることが多かった。次第に母と私が天下を手伝うことが多くなったが、私はすぐに並んで歩くことを恥ずかしがるようになった。今でも悪いことだとは思っていない。だって私は生きているんだ。
「スゴイ!ヤバイ!」
自宅に戻ると天下が奇声をあげながら直方体を早速分解し始めた。私達の部屋は1つしかないのであっと言う間に天下への誕生日プレゼントで埋め尽くされた。天下が少ない語量でありとあらゆる賛辞を送る。大半は極端にデフォルメされたロボットとか人形とかそういうもので、一応尖ったものは見当たらなかった。
天下はいいな
「きょうね。ライトくんがね!」
「いいから食べな、冷めるよ」
世の中には喋ることと食べることが同時に出来ない人間がいることを私は知っている。だから普段は天下が食事中にしたい話を先に聞いて、私が適当にアーメンみたいなポーズをとってから二人で無言でご飯を食べるように区切っていた。けれど今日はなんだか面倒くさかった、結果余計面倒くさいことになった。ラップに水分が付きすぎて水餃子みたいになってる焼き餃子を二人でつつきながらそれを私達は誕生日ご飯としていた。お母さんからは誕生日プレゼントとして1人ずつ中くらいの大きさのチョコレートが置いてあった。
「お母さん、遅くなるから、もう寝な」
「うん」
天下のいいところは直ぐに寝るところだ。言えばすぐに寝る。もしかしたら天下なりに私達に気を使っているのかも知れないが、聞いたこともないし聞きたくもないのでわからない。
洗い物をしながら考えた。廿先輩にも最上一にも私は誕生日を教えていない。大丈夫だ。私は祝われていないのではない、彼女達が誕生日を知らないだけだ、でも私が彼女達に誕生日をそれとなく伝えることが出来る日が来るのだろうか。私は廿先輩から殆ど2文字しか頂いていない。実際のところ喋っているのは最上一とばかりだ、廿先輩の100倍以上の文字数を貰っている。最上一が私の誕生日を知っていたらどうなったんだろう?では廿先輩は?クラスメイトには期待していない、そもそも私は彼らの名前を殆ど知らない。大丈夫、私は1人だって生きていけるのだ。彼らに認められなくても私は大丈夫だ。でも、今日彼らに投げかけられた3文字、悔しい…私がおまえらに何の迷惑をかけたっていうんだ。
もし、もし、いつも考える。私と天下は同じ顔をしている。もしくはしていた。子供の頃は同じ顔つきだった。でも小学校にあがる頃には私達は異なる顔つきになっていた。もし天下が普通だったら、天下はクラスメイトと仲良くなり今の学校と同じように山のような誕生日プレゼントを受け取っていたのだろうか。
もし、もし、いつも考える。私が天下と同じクラスだったら。私は誕生日プレゼントを貰えたのだろうか。
私は気がつくと餃子を包んでいたラップを延々と洗剤で洗っていた。私は洗剤まみれのラップをゴミ箱に放り込んだ。
体温が下がっていくのを感じる。違う、私と天下は違う。きっと私達は上手くいってても同じ顔立ち、同じ顔つきでクラスの端で二人して座っているだけだ。私達は祝われないことこそが普通なのだ。天下が今ああなのも、誕生日プレゼントにまみれているのも全部たまたまだ。
私はまだ高校生だけど知っている。大人は「子供だから仕方がない」と言われないだけの子供なのだ。天下がああなのも「仕方がない」し、誰かがメンヘラなのも「仕方がない」し、誰かが傲慢なのも「仕方がない」し、誰かが神経質なのも「仕方がない」し、誰かが運動音痴なのも「仕方がない」し、私達が貧乏なのも「仕方がない」し、私が孤独なのも「仕方がない」のだ。子供には希望が、未来があると言うけれど、その未来のある子どもが成長しても所詮そこらへんに居るおじさんおばさんぐらいにしかならないのだ。
どうして!?あの天真爛漫な、何もかも受け入れてくれた廿先輩が、あんなにも変わってしまった。ろくに友達付き合いが出来ない私とも友達になってくれた、孤独だった私の相手をしてくれたあの天使のような廿先輩。私を好きだと言ってくれた、世界でただ一人好きだと言ってくれた廿先輩。廿先輩がいない4年間のことは思い出したくない。私にとって廿先輩こそ全てだったんだ。4年間やっと会えたのに、最上一、あいつが変えたのか?また好きだと言って欲しい、誰でもいいから私のことを好きだと言って欲しい!
丁寧過ぎる皿洗いで私の指はふやけていた。天下はとうの昔に寝ていた。寝ている天下の顔は私とそっくりだ。寝ている間だけ天上天下は一体化する。私達は同じ人間なのだ。天下は幸せなのだろうか。私は生きてるだけだ、もう、生きてるだけでいっぱいいっぱいだった。
次の日、私は天下を向かえに行かなかった。私は最上一が住み込むゲームセンターに廿先輩と三人でいた。私はいつも通り2人の後ろで立っているだけで十分脂汗まみれになるのに、天下のことを考えると体の震えが止まらなかった。お母さんは働いてる、天下は何時まで私を待つだろうか、そもそも学級は何時まで預かってくれるんだろうか、電話しても誰も家にはいない、学級の先生達も多分私の電話番号を知らないと思う。天下は、天下には誕生日を祝ってくれる沢山の友達がいるから、知らない、どうなるのかわからない知らない。もう廿先輩に話しかけようともしない、ゲームもしない、私はただそこで震えるだけの地蔵になっていた。
その時だ。
「廿、昨日うちの部屋に傘忘れてったでしょ」
「あぁ…そだね、帰り振ってなかったから、あんがと」
私は天下のこと、お母さんのこと、誕生日プレゼントのことを全て忘れた。最上一の部屋、このゲームセンターに住み込む最上一の部屋は直ぐ近くにあるはずだ。廿先輩は毎日このゲームセンターに来ている。けれどそれは、もしかすると、私の思い違いだったのかもしれない。廿先輩は、毎日、最上一に会いに来ていたのかもしれない。私も毎日このゲームセンターに来ていた。だが、私は天下を迎えに帰っていた。廿先輩は、その後、毎日最上一の部屋に、
「え?傘って、どういう…」
私は今日初めて言葉を発したような気がする。動揺して、知りたくないことをストレートに聞いてしまった。最上一は、明らかに「しまった」という顔つきで
「あ…いや…ほら…傘ってよく忘れるでしょ…」
そういうことじゃない、私が聞きたいのはそういうことじゃない。なんで廿先輩の傘が「おまえの部屋」にあるのかを聞いてるんだ。誤魔化すな、聞きたくない、言葉を濁すな、私何してるの。
「てめぇには関係ねぇだろ」
4年ぶりに目を合わせてくれた廿先輩の発した言葉は、何よりも力強く、何よりも汚らしかった。それは、他に意味を取り違えようがなく、私を壊すには十分なパワーがあった。
「てめぇ…もう時間だろ、帰れよ」
敵意を剥き出しにした廿先輩が私の頭上よりも40センチは上の位置から、タンを吐く代わりに言葉を吐いた。
「はい…帰り…ます…」
家までは歩いて帰った。私はまだ死んでいない。
廿先輩は私の唯一の天使、私の人生で唯一私を好きだと言ってくれた天使、私だけの天使、私のものじゃなかった、最上一、全部おまえが悪いんだ、全部おまえだ、私だけの天使、どうして、私の廿先輩を取らないで、私には廿先輩しかいないんだ、最上一!最上一!
暗い部屋でつけっぱなしのバラエティ番組に被せて天下の大きな泣き声が聞こえてきた。学級の先生に連れられた天下は泣き過ぎてラマーズ法みたいな呼吸をしていた。先生に理由を問われたが、私は頑なに話さなかった。そもそも理由なんて無いのだ。私が悪いんじゃないし、私は何も悪くないし、私だって生きてるし、私は天下じゃないし、そう、天上天下は一人じゃないのだ、死にたくない
「こんな奴と一緒にするな!!」
私が初めて出す大声に先生は驚くと同時に手を振り挙げたが、先生は私の目を見たまま振り下ろすことはなかった。
「んぶ!ふぅおねぇ!ぉねぇちゃあん!はあぁっあっは!んぉねぇちゃあ!んぶぅふ!」
2人の動作を理解しない天下が私をラマーズ法で呼び続ける。天下、私と同じ顔をした、私より数時間あとに産まれた私の妹、同じ服を着せたらどっちかわからないね、商店街の老人はそう言い放った、見分けが付かないなら平等に扱え、私は天下の-----------、たった数時間先に産まれただけで、天下が普通じゃないだけで、同じ顔の天下の前を歩かなければいけない、報われるべきは私だ、祝われるべきは私だ、同じ誕生日なのに、同じ姉妹なのに、なんで天下だけが祝福されて、悲しい時に泣いて、嬉しい時に笑えるんだ、私はまだ生きている、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない、
「天下…もう大丈夫?」
「うん!」
「天下、いつも話してる廿先輩と最上先輩のこと覚えてる?」
「なんで?おぼえてるよ」
「お姉ちゃん、今からあの二人を壊してくるね、お留守番お願い」
「うん!わかった!」
最上一だ
最上一だ
最上一さえいなければ廿先輩は廿先輩のままだったんだ。最上一を壊したら、廿先輩は帰ってくるだろうか?
明らかにこの街の人口に対しては多すぎる街燈の下を、私は休みなく駆け抜けた。疲労感はない、次第に全ては快感に変わってきた。等間隔に並ぶ街燈の間を強く輝く星が点いたり消えたりしている。中学生活最後の授業、その帰りもこんな感じだった気がする。街燈と星が明るさを競い合う、そう、あれは「施し」だ。中学卒業目前の正真正銘最後の授業だった、ただそれだけの理由で英語講師が選ばれた。それまでどの授業でもロクに生徒に相手にされなかった派遣講師が赴任最後の授業であり、生徒達にとっても中学生活最後の担当授業というだけで、生きる希望を再燃し沢山のパネルと写真を用意して私達の明るい未来を見せた、当たり前のように全クラスで無視されたパネル達は私達のところにまわってくるまでには消失していた。英語講師は学校では生きていたのだろうか?私と同じで瀕死だったのかもしれないし、大人だからもしかしたらもう死んでいたのかもしれない。全ての善意が無駄にされた英語の授業、同じようなことをしても全てを笑いに変え、生徒に愛される講師もいるし、愛されはしなくても生徒を歯向かわせない空気の講師がいる。空気?空気って何だろう?等間隔で並ぶ街燈は夜の空気だ、力のない星はそこにいることすらも知られなくなる、高層ビルの下では街燈がいらない、誰にも愛されないし、必要ともされない。生きてるって輝くことなんだろうか?生きてるって強いことなんだろうか?私達は英語講師を歓迎した。意気消沈した英語講師を笑顔で迎えた。英語講師の最後の担当授業と、私達の中学生活最後の授業が偶然一致したからだ。別に他の科目でも良かったのだろうがサイコロは彼を選んだ。英語講師は教員室までパネルを取りに走り、私達は中学生活最後の授業をパネルと写真、そして講師の涙の演説で締めくくった。受け取るだけじゃない、こちらからは寄せ書きを分け与えた。テーマははっきり覚えている、「先生の授業から私達が学んだこと」だ。私は何を書いたろう、確か先生のおかげで英語を好きになりましたとかそういうことだった気がする、別に英語は好きじゃない。英語講師は号泣していて少し気持ちが悪かった。大人も泣くのだとは私は知らなかった、大人も子供なのだ。一年間、英語講師は瀕死だったのかもしれない、でも最後の一時間は、確実に生きていたのだ。これは善い行いだったのだろうか?これは一人の人間を生き返らせる魔法のような善行だったのだろうか?全ての発起人はクラスで最も輝く女だった。100万回生きたねこを読んて「私、犬の方が好き!」と言うような女だ。普段は輝いていない私みたいな星に対して、まるで見えていないかのように振る舞う女。けれど夏にもなる頃には私も気が付いた、「見えていないかのように」じゃない、「見えていない」のだ。私は別に何をされた訳じゃない、最後の授業だってあの女が生まれ変わった訳でもない、ただ普段通りに生き、気まぐれに英語講師を受け入れたのだ、私はあの女が嫌いだった。あの女は英語講師を救ったのかもしれない、英語講師を生き返らせたのかもしれない。けれど私には分かる、あれは「救済」ではない、あれは「施し」だ、でも「施し」が英語講師を生き返らせたのだ。私は今、死にかけている、高校生になった今、あの女はどこにもいない、私は悪くない、私は何も悪くない、ただ一言、誰でもいいから、私のことを好きだと言って欲しい、あの女は嫌いだ、でも、私も「施し」を受けたい、
最上一の住み込むゲームセンターにつく頃には、私は雨に打たれたようになっていた。考えてみたら最上一の部屋がゲームセンターのどこにあるのかは私は知らなかったし、部屋に入って今正に最上一と廿先輩がいたとしたら私は即死してしまうような気もしたけれど、部屋は案外すぐに見つかったし、最上一は1人だった。
「やあ、どうしたの、天上ちゃん一人なんて珍しいね、汗、大丈夫?」
「はい、あの、[傘]を、忘れたような気がして」
「傘?ゲーセンの中でかな?ちょっと今急いで探してみようか、終電のこともあるし」
「いえ、もういいんです傘なんて…最初からそんなものなかったような気もしますし…それに、電車もいいです、乗ってきませんでしたから」
「…」
「あの…部屋…上がってもいいですか?」
「話なら聞くよ」
誰とも話せない私は、最上一とは普通に話せた。廿先輩が2文字しか返してくれない今、どこにも存在しない私にとって世界で唯一話をしてくれる人が最上一なのかもしれない。
「…」
最上一はスマホを弄り続けていた。最上一と会話が無言で過ごすのは初めてかもしれない。それでもいい、私はお喋りをしに来たのではない。けれど、意外にも先攻は最上一だった。
「廿と子供の頃仲良かったんだってね?」
「今は仲良くないみたいな言い方、やめてもらえますか?それに今でも子供ですよ」
「高校生は子供かな?確かにそうかもしれないね」
「今度は私から質問させて下さい。私がいつも帰ったあと、廿先輩はここに来てるんですか?」
「天上ちゃんだって今ここにいるじゃないか。天上ちゃん、今日は随分ストレートだね」
「誤魔化さないで下さい!!」
「う〜ん、そうだね、僕達はいつも一緒かもしれない。はじめて会った時もそんな感じだったよ」
…!!この…調子に乗りやがって…!
「最上先輩は!……廿先輩とはどういう関係なんですか!?」
「それは子供には話せないな。天上ちゃんは[子供]なんだよね?」
「かっ…あ…」
許せない!許せない許せない許せない!!汗を拭った手に血が付いてるのに自分で驚いたが、知らないうちに唇を噛み切っていたらしい。マンガみたいに興奮して鼻血を出している訳ではなかったが、顔一杯から色の付いた色んな液がまっすぐ飛び出して今にも最上一を打ち抜きそうだった。
「それとも天上ちゃんはやっぱり大人だったのかな?」
「私には男友達なんていません!!そもそも私は!学校に!一人も友達なんていません!!中学も!高校も!!私の友達は廿先輩だけです!!!」
私は隠し続けていた事実を初めて人に暴露した。生まれて初めて他人に暴露した。けれどそれは、秘密にしてはあまりにも周知の事実だった。私自身はそれを実に上手く隠匿しているつもりでいたが、告白してみればなんてことはない。考えてみれば私に友達がいないことはクラスメイトの誰もが知っているのだ。こうも毎日のように来ていれば最上一だってわかっていたはずだ。星は明るさも大きさも様々だが、「無」は誰が見ても「無」だった。無は隠匿しようがない。私は何をしていたのだろう。いつしか私の顔からは鼻血ではなく、隠匿しようがない程の量の涙が出ていた。私はまだ死んでいない、でも、無はそもそも生きているんだろうか、
「ひどいな、少なくとも僕は天上ちゃんの友達のつもりだったんだけどな」
「あなたなんか!!あんたなんか大嫌いだ!!!!!!!ああああああ!!!」
最上一は私の顔から吹き出す大量の汗と血と涙を見ても全く動じなかった。なんでこんなに冷静なんだ!!悔しい!!私が可愛そうだとは少しも思わないのか!?悔しい!!私がムカつくとは少しも思わないのか!?悔しい!!私のことは少しも想ってくれないのか!?私は自分が何故激昂しているのかよくわからなくなってきた。私は自分が何故奇声をあげているのかよくわからなくなってきた。二人しかいないゲームセンターの中に自分のものとは思えない奇声だか気勢だかが鳴り響く、私は気が付くと最上一の両腕を力一杯壁に押さえつけ自分でもわからない何かを怒鳴り続けていた。
「ダイキライダ!!ダイキダイダ!!!うああああ!」
「僕は君と喋ってると楽しいよ」
「嘘だ!!」
「嘘じゃない」
「絶対に嘘だ!!二人共私を嫌ってる癖に!イヤだぁあ!!!嫌いだって言えぇ!!!!!」
「好きだよ、廿も絶対に君のことが好きだよ」
「んッ」
私は何だかわからないうめき声をあげると、最上一に転がりながら全身でしがみついていた。
「んぶ!きらわないで!!っご!ごえんあさい!はあぁっあっは!ぎらわないでええ!んぶぅふ!」
身体の中からカロリーが全部消えて物理的に消えてなくなるかもしれない、そのぐらい、私の謝り方はとにかく「全部」だった。
部屋に駆け込んできたのは全身びしょ濡れの廿先輩だった。
あああ
私の全生命を懸けて絞り出した涙に汗に血に涎、それと負けぬ液だらけの廿先輩を、私は190センチ下に転がりながら呆然と眺めていた。
“天上ちゃんが今部屋に来てるよ”
最上一が廿先輩に送ったのはこの一文だけだった。この世の終わりのような勢いで掴みかかってくる廿先輩を最上一は押し止め、私はすぐに今日の全てのあらゆる侮辱、そして廿先輩の最上一に触れたことを地面に額を擦りつけて詫び続けた。
この4年間、廿先輩を変えたのは最上一ではなかった。廿先輩は留学中の3年間、ただひたすらクラスメイトからのいじめに耐えていたのだ。変わっていなかったのは最上一の方だ。変わっていない廿先輩を求め続けたのは私の方だ。私は廿先輩にろくに話しかけることが出来なかったが、その逆はそれ以上だった。私の目を見つめながら廿先輩は震える声でこう言った。
「私の一を取らないで…私には一しかいないんだ…」
四王天廿も不安を感じることがあるのだ。
何故そんな当たり前のことを私は想像できなかったのだろう。私は私の中の四王天廿を膨らませ続け、想像通りの反応をしない四王天廿に暗に不満をぶつけ続けていたのかもしれない。
私は私が世界で一番不幸だと思っていた。
私は私を無だと思っていた。
では無の私にすら話しかけれない憧れの廿先輩は何なんだろう。
うちのクラスに無は何人いるんだろう、学年には、学校には、街には、
始発のホームで彼女は言った
「あなたとは友達になれると思ったのに」
乾いた白米はそのままだった。床で眠る天下に布団をかけると、天下は勢いよく目を開けた。
「おかえり、おねえちゃん」
「うん、ただいま、寒くなかった?」
「だいじょうぶー」
「ごめんね、私、あの二人、壊してこれなかったよ」
「しってるよ、おねえちゃんはそんなことしないもん!」
「…ごめんね…昨日迎えに行かなくてごめんね…辛かったよね…寂しかったよね…こんなお姉ちゃんじゃなければ良かったのにね…」
「んーん、わたしおねえちゃんがイイ!
わたし、おねえちゃんがせかいでいちばんすき!!」
|